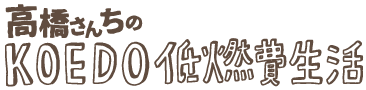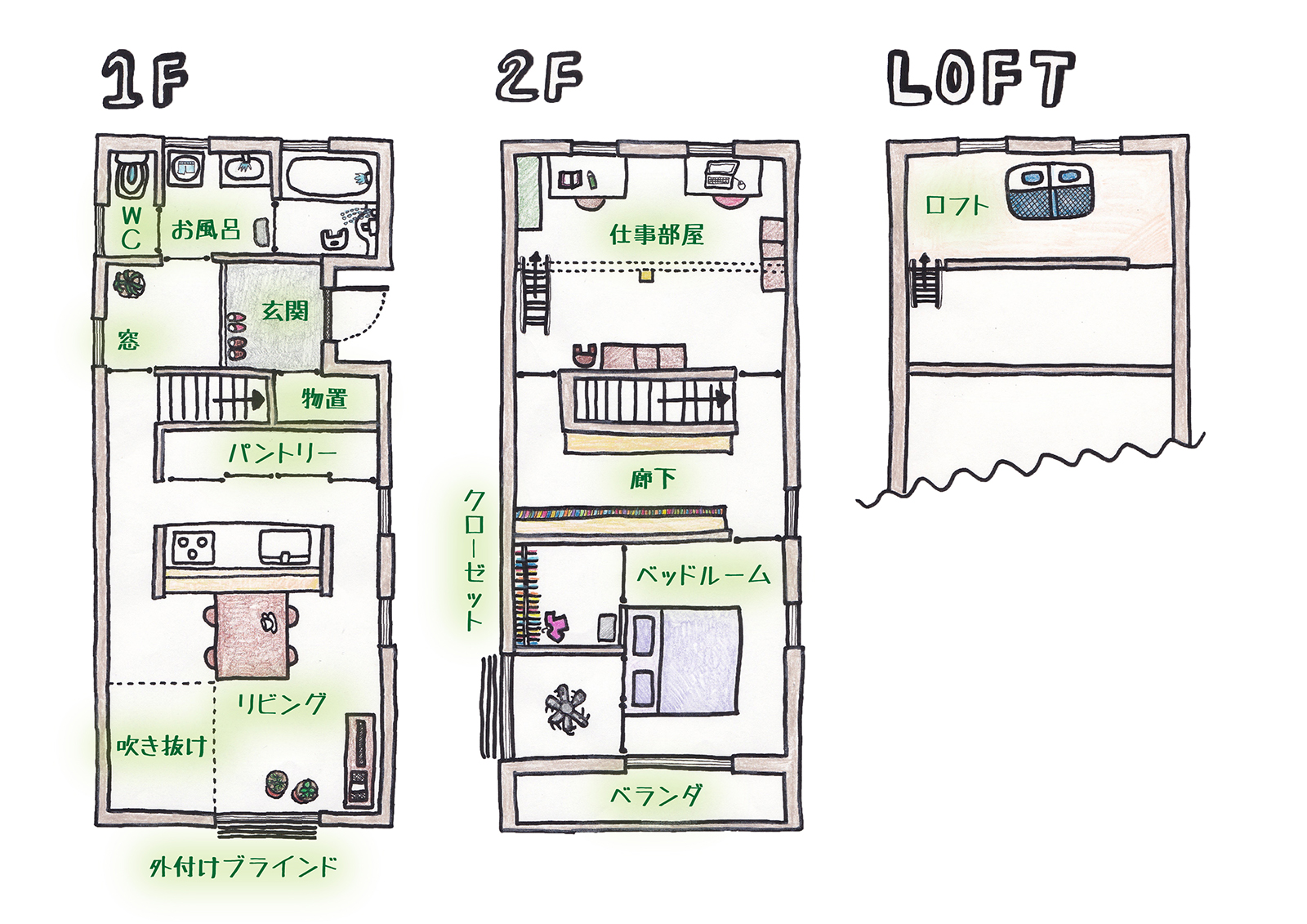まだ5月だというのに、夏のように暑い日も増えてきました。今回は少し視点を変えて、学校の断熱について書いてみます(←本の原稿の〆切前であたふたしているまさきさんから聞き取って、ゆみがまとめました)。
前半はこれまでも書いてきた断熱改修ワークショップについて、後半は、学校と断熱の関係(学校関係者のアンケートあり)です。
広がる学校断熱ワークショップ
僕が学校断熱に興味を持ったのは2018年ごろのことです。最初は、岡山県津山市の公共施設を担当する職員の方が、学校のひどい温熱環境やかさむ光熱費をどうにかしたいと、個人でお金を集め、工務店の協力のもとDIYで一教室を断熱しました。そんなことができるのかと驚きました。
学校は、最近建てられたものを除き、断熱ゼロの建物がほとんどで、冬は極寒、夏は酷暑です。そこに気候変動の影響も加わり、教室の環境は勉強どころではなくなる日も増えています。学校全体をすぐに断熱改修するのはなかなか難しいなか、まずは効果を感じてみよう!というのはとても良い取り組みだと思いました。
あちこちで再エネ&省エネの講演をする中で、その津山市の学校断熱の例や、その意義について紹介しまくっていました。それがきっかけとなり、長野県の白馬村で、「自分の学校でもやりたい!」という生徒たちが声を上げました。その結果、生徒たちが主体となって、周りの大人たちを巻き込んだ断熱改修ワークショップが白馬高校で行われたのです!(そのときの様子はこちら)。

一教室ではあるけれど、このようなワークショップで大事なのは、参加して、断熱の効果を体験することです。DIYの断熱改修でも、真夏・真冬には劇的に効果が実感できます。そうすると、他の教室や家でもやってみたり、断熱が広がるきっかけにもなります。
生徒を巻き込んだワークショップは、教育効果も生んでいます。断熱材なんて大人も触ったことのない人がほとんど。それを、自分が学ぶ教室を改修して、その効果を確かめることで、学びにつながるのです。
その後、長野をはじめ、各地に生徒や市民グループが主体の断熱改修ワークショップが広がっていきました。埼玉では、以前も紹介した工務店のネットワークが中心となった動きもあります(詳しくはこちら)。
共通しているのは、「学校の温熱環境をどうにかしたい!」という思いです。これまで、全国の小学校から大学まで、全国40か所以上で断熱改修ワークショップが行われてきました。
ワークショップだけでは限界がある
一方で、ワークショップ形式や、DIYでの取り組みには限界があります。DIYでかかる費用は、一教室あたり60〜100万円くらい。多くはクラウドファンディングを行ったり、工務店などの持ち出しで、費用を下げる工夫を重ねてきました。
しかし、学校も教室も広いので、100万円集めても1教室しか断熱できません。子どもたちの健康や学びの環境改善を考えると、本来は行政が予算をちゃんと取ってやるプロジェクトではないでしょうか。
学校の温熱環境の現状と断熱事情
この春、NPO法人School voice project が行った、学校の冷暖房調査では、教室を適切な温度に保つために、エアコンをうまく活用できていないという結果が出ています。猛暑対策でエアコンを設置したものの、様々な理由で効果的に使うことが難しいというのです。
しかし、エアコンと断熱をセットで考えれば、ほとんどが解決できる問題です。「暑さ寒さはエアコンさえつければなんとかできる」という誤った常識を、学校から変えていければいいなと思います。2022年に行われた第1回のアンケートについては、解説記事を書いているので、参考にしてください。
予算がないと言うけれど…
「学校の断熱改修が必要」というと、必ず「予算がない」という話になります。実際、自治体の予算は限られていて、壊れたトイレの改修など、優先しなければならないものがあります。文科省では学校の改修予算は出ているものの、額は十分ではないため、なかなか断熱にまで予算が回っていません。
文科省は「予算枠があるから、あとは学校ごとに判断してやってください」という姿勢ですが、それでは、全国で暑さ、寒さに悩んでいる子どもたちは救われないわけです。
全国の学校がきちんと断熱されるためには、国は本気で「断熱のための予算」を確保して推進する必要があります。予算、予算と言いますが、政府の方針が変われば予算の確保は難しくありません。
実際、2018年の猛暑の後、政府が学校にエアコンを普及させる方針を決め、予算を取ったことで、学校のエアコン普及率は一気に上がりました。断熱だって、その重要性が認識されれば予算を取ることは可能だと思います。
先ほどのアンケートからもわかるように、学校の建物は断熱がされていないため、エアコンで涼しくも温かくもなっていないという実態があります。温度ムラも大きく、教室内で暑いところと寒いところが極端に出てしまい、快適にはなりません。学校の建物は隙間だらけで、窓、壁、天井、あらゆるところからエアコンの冷気や暖気がダダ漏れで、穴の空いたバケツに水を入れ続けている感じになるのです。

そうすると光熱費が上がり、予算が足りなくなってエアコンを止めたり、ギリギリまで我慢するという事態になってしまいます。それではエアコンを設置した意味がありません。でも断熱とセットでやれば、快適性が上がり、光熱費は下がるのです。
「学校を断熱改修したら、光熱費の削減で元は取れるのか?」という費用対効果の疑問も出ます。学校は週末、夏休みなどの長期休みもあって、公共施設の中では稼働率が低い場所です。そのため、断熱改修をしても光熱費削減効果が少ないと言われます。

でも、学校断熱の視点は、子供が毎日過ごす場所、勉強する場所を過ごしやすくして、命や健康を守るということを第一に考える、ということです。学習しやすい環境を作るのは大人の責任です。指がかじかんで鉛筆が持てない、暑くて熱中症になりそう、という環境で勉強に集中できるわけがありません。学校の劣悪な環境を改善しなければならないのは、費用対効果を考える以前の問題です。
また、学校は災害時の避難所にもなります。しっかり断熱されていれば、災害で真夏や真冬に停電しても、避難した人が暑さ・寒さをある程度しのぐことができます。そのような意味でも、学校の断熱は重要です。
これからの季節、学校では夏の熱中症対策が急務になっています。すぐに建物全体の改修ができなくても、対策を取ることはできます。最も効果が大きいのは、建物の大きい窓の外にブラインドをつけることですが、それが難しい場合は内側に遮熱カーテンやハニカムブラインドを設置することでもある程度の効果はあります。
それに加えて、最上階の教室を優先して、天井断熱を早急に全ての学校ですべきだと思います。それだけでも劇的に環境は改善し、エアコンの効きもよくなります。
資料・断熱ワークショップの広がり
・青森県青森市の原別小学校で行われた断熱改修ワークショップ
つい先日、市民の方の提案で小学校の断熱改修を行った青森市の小学校の情報です。当日の様子が書かれた記事(朝日新聞・有料記事)も参考にしてください。
・東京都葛飾区の取り組み
自治体でも断熱改修を行ったところが出てきています。
・神奈川県藤沢市小糸小学校の実践例
市民グループと行政が共同で断熱改修ワークショップを実施した例です。
断熱改修後は、子どもたちが効果を感じているとのこと。そして、藤沢市では、このワークショップを行った教室を議員や行政職員が見学したことがきっかけとなり、新たに公共施設を立てる際や、大規模改修する際には、一定の断熱性能を目指すという方針が掲げられました。
・実践例のまとめとして、「学校建築脱炭素研究会」というグループがサイトを立ち上げているので、こちらも参考にしてください。
学校の断熱改修は、子どもたちの健康、命、そして学びを守るために不可欠です。教育や断熱に関わる人が協力して、このような取り組みを参考にしながら、全国に広げていけたらと思います。
おわり